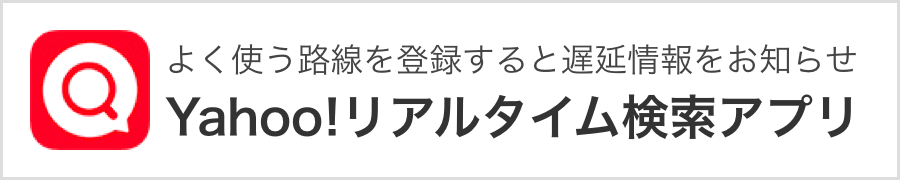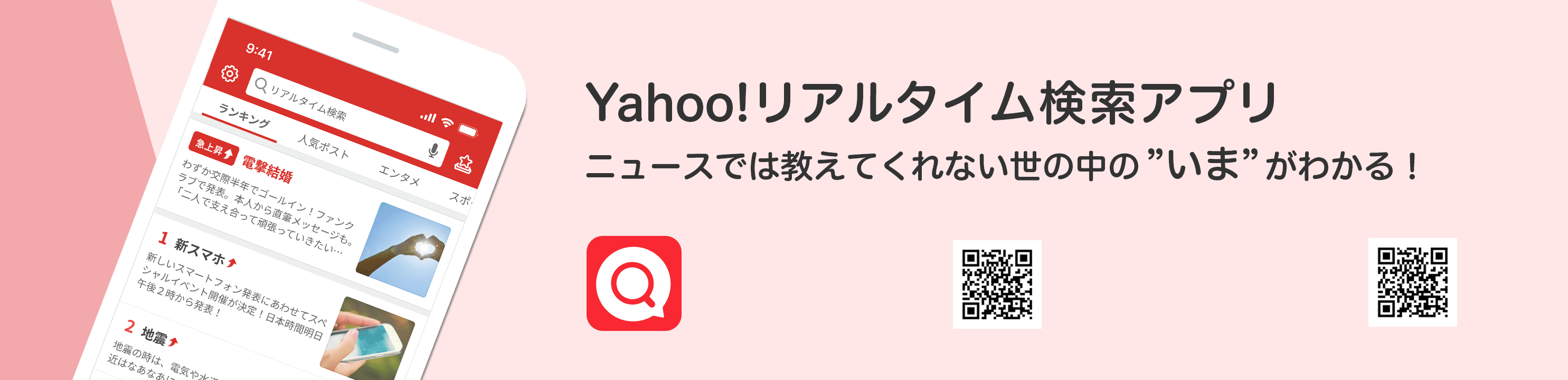ポスト
#恵慶法師 の #百人一首 歌「八重葎…」の歌は『#拾遺和歌集』秋 収載 その前に置かれているのは #紀貫之 の #醍醐天皇 の時代の屏風歌 " 秋 "←の音読み " しゅう "←を今度は " 集 "←にも変換するのかな?と私は思った。 👇 荻の葉の そよぐ音こそ 秋風の 人に知らるゝ 始(はじめ)なりけれ (荻の
メニューを開く百人一首48 #恵慶法師 は男性歌人のサロンとか歌人コミュニティの常連だったらしい 『#拾遺和歌集』秋 に採られた歌は そんな参集の場の雰囲気が感じられる。 詞書は 河原院にて 荒れている宿に秋が来ている という趣向で人々が詠んだので 👇 八重葎(やへ むぐら) 茂れる宿の さびしきに 人こそ見
みんなのコメント
メニューを開く
葉が そよそよと そよぐ音こそは、秋風が人に自然に感じられる始まりなのだった) 荻←は 水辺に自生するイネ科の多年草、ススキに似るが葉や穂は大きい。 平安中期になると荻の葉音が、人の訪れ←と解されるようになった。 秋←が 音で衆(=たくさんの人.大勢)←に変換できるとすると秋は荻の そよぐ音